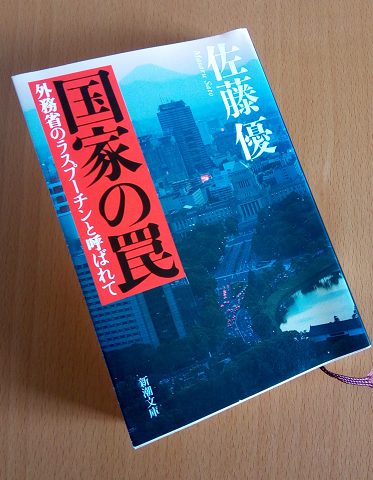
最近読んだ、『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(佐藤優、2007)。
外交機密上から全てを語れないにしても、文章から溢れ出る知力・精神力・洞察力・分析力・教養・ユーモア・冷静さなどが恐ろしい…
同時に、「こうした人が世界的政治エリートと対等に渡り合える外交官なのか…」と納得。
これだけの人を外交の場から排除してしまったことが、いかに日本の国益を損うことになったか、を想像するのもまた恐ろしい…
「出る杭は打たれる」嫉妬ヤバめの村社会日本では、どれだけ国益となっても「現状維持を望む」組織から睨まれたらアウトなのかな…
既得権益保持者による足の引っ張り合いが凄そうだから。
現日本は他国との交渉でほぼ毎回、短期的利益を優先するあまり長期的国益を見失っていますが、
佐藤氏の排除もそれと似ているような気がします。
本書で印象に残った文章に(佐藤氏の発言ではありませんが)、
日本人の実質識字率は5パーセントだから、新聞は影響力を持たない。ワイドショーと週刊誌の中吊り広告で物事は動いていく(p97)
というものと、
外交官には、能力があってやる気がある、能力がなくてやる気がある、能力はあるがやる気がない、能力もなくてやる気もないの4カテゴリーがあるが、そのうちどのカテゴリーが国益にいちばん害を与えるかを理解しておかなくてはならない(p85)
というものがありました。
後者については、「能力のない人間が国益に害を及ぼす」旨が強調されていました。
他にもこの本を読んで、ロシアはイスラエルとの関係性が深いことを知りました。
イスラエルにはモスクワよりもロシア情報が集まってくる場合があるらしい…ただそれは佐藤氏のように人脈が豊富で有能な場合だと思いますが…
佐藤氏を初めて知ったのは10年以上前の新聞記事だったと思いますが、おそらく氏が作家活動を始めた頃だったと思います。
その頃は外交官時代のような、睡眠時間3時間・何かあればすぐに動けるような状態ではなかったようですが、国を背負って生きる様は変わっていない印象でした。
この本の内容は重いですが読みやすく、世界レベルのビジネスエリートと渡り合う生き様には凄みがあり、
氏の本を読めば読むほど氏の持つ恐るべき能力を認識してしまいます。


